『世界の尾張とベリースウィートワンダーランド』

えみる:抽斗さんの『【企画】 私を街へ連れてって 【第一回テーマコンテスト】』に参加しました。
作中に実際の地名を使い、その地名に必然性を持たせること、というテーマでオリジナルの小説を募集します。投稿期間は2月いっぱいです。
— 抽斗@私を街へ連れてって (@hikidashi4) 2017年1月28日
【企画】 私を街へ連れてって 【第一回テーマコンテスト】 | 抽斗(ひきだし) #pixiv https://t.co/QMS6Y09zbv

山田:pixivに先日アップしましたが、同じものをこちらにもアップします。経緯やこの作品に関するネタについては、次回の更新で(*´ω`*)
『あの喫茶店』、みんな知ってるよね。
あるメニューを頼んで『登頂』できれば、甘い想いが実るみたい。
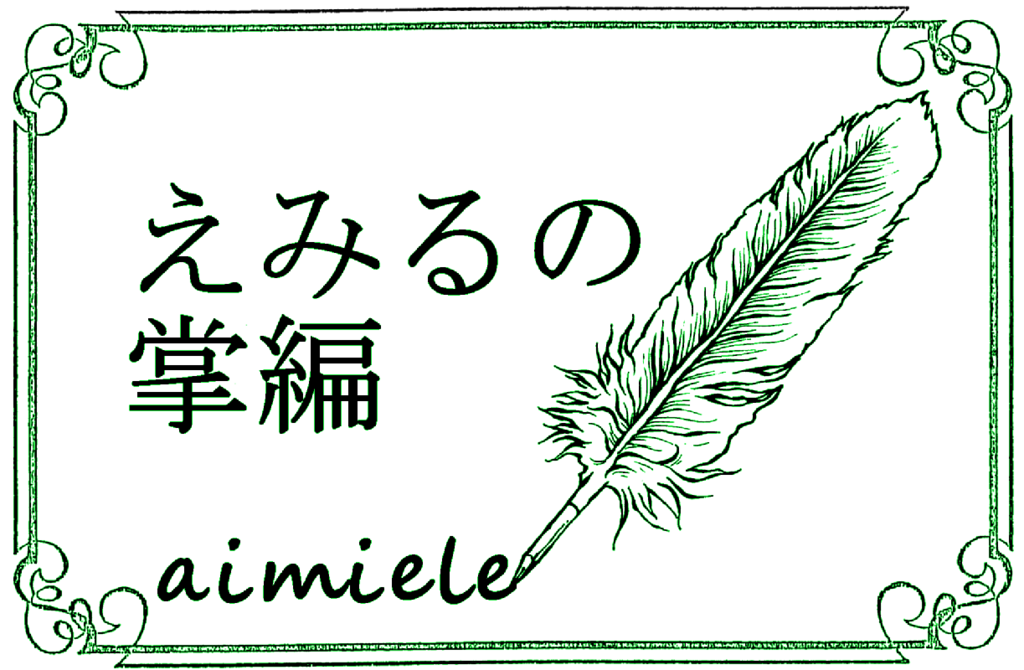
今夜も『朝までチェリーブロッサム!』、聴いてくれてありがとう。それでは占いのコーナーに行きましょう。まずは水瓶座のあなた、今後の人生を左右する素敵な出会いがあるでしょう。勇気をもってその一歩を踏み出してみて。でもときには逃げ出すことも必要かも!?
ピコン。
ラジオアプリで深夜の放送を聴いていると、オカルト研究会の掲示板に新しい書き込みがあった。わたしはベッドの上でごろんとうつぶせになり、充電ケーブルの刺さったスマホを眼前に構える。投稿者は『7ch』というアカウント。
大村部長は言っていた。
『彼女の正体は誰も知らない。OBだとは言われているけど、特定はされていない。しかし、その取材力、知識量、文章力、すべてが卓越しているんだ。オカルト研究会はみな、彼女のことを信奉している。君もすぐにその魅力がわかるさ』
部長のいうとおり、その謎めいたアカウントがFaithbookに投稿する都市伝説に、わたしはすぐ虜になってしまった。逢ったこともない知らない人。この画面の向こう側にどんな人がいるのかも知らない。Fictionな存在かもしれない。それなのにまるで傍で語りかけてくるかのように、彼女の文章は謳う。
ただし、ちょっとだけ、わたしは彼女のことが嫌いだった。それは大村部長があれほど眼を輝かせて彼女を讃えていたからだ。嫉妬というやつ。オカルト研究会所属であっても、高校二年生のわたしは年相応の恋をするのだ。
「今日はなにかなぁ」
スマホを操作して、彼女の投稿した記事を開く。タイトルは『ななふしぎ』。ここ数ヶ月、彼女は稀によくそういった投稿をしていた。これで七つ目。これでおわり。
スワイプをすると、文字列が表示された。
『あの喫茶店』、みんな知ってるよね。
あるメニューを頼んで『登頂』できれば、甘い想いが実るみたい。
『世界の尾張とベリースウィートワンダーランド』
『あの喫茶店』
名古屋に住んでいる者ならば誰もが耳にしたことのある、とても有名な飲食店だ。『甘口いちごスパゲティ』『納豆サボテン卵とじスパ』『甘口バナナスパ』……、少しネットを漁るだけでショッキングな画像が次々と現れてくる。
「……うっ」
麺に練り込まれた甘味。山盛りなパスタ。完食できた者はその喫茶店の名称にかけて『登頂者』と呼ばれ、完食できなかった者は『遭難者』と呼ばれる、魔の境地だ。
『帰りに行こうぜ!』
オカルト研究会ではよく帰り際にそういう話題が出る。地下の環状線を利用すれば、ちょうどよい距離に高校が立地しているからだ。しかし、わたしは行ったことがない。最初にそのお店の話題をネットで見たときから、とても食べ切れる自信がなかったのだ。わたしが好きなものといえば、おせんべいやおかき。こういう甘味はどうしても苦手で、小さい頃から両親には誕生日のケーキを断っているほどだった。
『あの、先輩は行かないんですか?』
ある日、オカルト研究会の一部の男子が登りに行ってしまったあと、わたしは憧れの大村部長に話しかけたことがある。彼は複雑な表情をしながら、友達を見送っていった。帰り際に近くの霊園やオカルトスポットに行くときは眼を輝かせているのに、その日はちがったのだ。
『……帰って、文化祭で出す部誌の原稿を書かないと』
『とかいって、甘いものが苦手なんじゃないですか?』
『そ、そんなわけないんだろ!』
ちょっとからかってみただけなのに、顔を真赤にして反論する大村部長。いつもはクールにオカルト研究会を取り仕切っているのに、それはわたしだけが見ることができた無防備な表情で、きゅんとしてしまった。なお、わたしはこの部活の編集担当であるため、部長が誰よりも早くきちんと原稿を提出していることは知っていた。
妙な沈黙が流れてしまった。
部活で借りている会議室には、夕日が差し込んでいる。部長が鞄に、今日の議題で使ったムーを片付けている。遠くで吹奏楽部の演奏が聴こえ、たまにカキーンという野球部の音も混じる。文化部の面々はほとんど帰ってしまったのか、廊下に人の気配はない。
二人きりだ。
オカルト研究会、わたしはいま憧れの人と二人きりであることを強く意識してしまった。心臓の音が部長にも聴こえてしまいそうなくらい高鳴り、頭が沸騰しちゃいそうだった。
『そういえば、部長は……』
『ん?』
――好きな人はいますか?
そう訊こうとした瞬間、吹奏楽部のトロンボーンが音を盛大に外した。わたしの想いは空気を震わせることはなく、胸の奥に舞い戻って、どっしりと堆積した。
『なんでもないです』
『そうか。なら、大村君も早く帰りなさい。日は長くなったけど、暗くなるのはまだ早い』
一緒に帰りませんか、先輩のオカルト話聞きたいです――、と勇気のあるわたしならそう言ったのかもしれないが、わたしの家は校門時点で部長と反対側なのである。そして部長はわたしの家を知っている。なぜなら彼の手にしているムーはうちの書店で買ったものだから。わたしが店番をしているときに買ってくれた、たいせつなものだ。
『では、部長、また部活で』
『ああ、中間試験があるからしばらくあいだが空くが』
『部誌の執筆、がんばって下さいね』
それだけ言って、わたしはオカルト研究会の部屋をあとにした。早足で廊下を歩く。部長と話すのは楽しいが、もし追いかけられてもう一話題でも振られたら、余計なことまで言ってしまいそうだった。ダメだと自分に言い聞かす。わたしはいまのオカルト研究会が大好きなのだ。もし部長への想いに追い縋って無残にフラれでもしたら、もうあそこにはいられない。
「せんぱい……」
ほんの数ヶ月前の夕焼けの部室から、自宅のベッドに帰ってきたわたしは、スマホをポチポチと弄っている。あれから何度か部長と話すことはあったが、あくまで同じ部活のメンバー同士の距離感で、それが縮まる素振りすらない。ちなみに彼は文化祭が終わっても、『原稿が……』という言い訳で、登山から逃れていた。
そんな先輩も、あと一ヶ月もすれば卒業してしまう。受験勉強のために部活をやめる者は多くいるが、先輩は熱意のためか、なぜか他の誰よりも一生懸命に部活をしていた。受験勉強は大丈夫なのかと思うほどだった。というか、『原稿が……』なんて言い訳せずに受験勉強って言えばよかったのに。
そういう抜けてるところも大好きだった。
だから、いなくなるのは寂しくてたまらない。
大学はどこにいくのだろう。遠くなければいままでどおり部活にも顔を出してくれるかもしれない。でも、大学には大学の出逢いがあるはずだ。勉強やバイト、サークル活動だってあるだろう。たとえ近くの大学に行ったとしても、距離はいままで以上に離れてしまう。かたくなに縮まらなかったそれは、離れるときはいつだってたやすい。
「勇気を出さなきゃ」
わたしはスマホを正眼に構えて、テキストの入力画面を開く。しかしそれは先輩宛てではない。勇気の一言でそれができるのであればこんなことにはなっていないし、こんな状況においてその一言でそれができるのであれば、それは自棄っぱちである。
わたしが頼るのは――。
『初めてお目にかかります。わたしは現オカ研に所属をしている河村という者です。いつもあなたの投稿する都市伝説を楽しく読ませていただいております。さて、きのう投稿された件ですが、わたしひとりでは勇気が出ず、もしよろしければ、登山をご一緒してもらえないでしょうか……』
Faithbook掲示板の機能を使っての個別メッセージ。送ってから、嫌な汗が背中を伝った。出過ぎた真似をしてしまっただろうか。この掲示板の伝説的なアカウントにこうして直接お願いをするだなんて。そして、まだ顔も知らない人にそんなお願いをするだなんて。
しかしわたしにはこの策以外には考えられなかったのだ。
先輩も尊敬する彼女のおかるとぱわー!を信じて、それに賭けてみることしか。このタイミングであの都市伝説が投下されたこと、そして登山というわたしにとって高いハードル。これはきっと運命だ。水瓶座の占いだって、一生を左右する出会いがあると言っていたことだし。
※
ありがとう、河村さん。
わたしが書き込んだ都市伝説に興味を持ってくれて、とても嬉しいです。わたしでよければ、ぜひ一緒に登山に行ってみましょう。実は、わたしまだ行ったことがなくて、一度行ってみたかったんです。いまのオカ研のお話も聞きたいな。
※
「はじめまして、河村さん」
「ひゃあ」
はじめてあったその女性は、ほんとうに綺麗なひとだった。雪のように白い肌、すらっとしていて背が高く、雑誌で見たような最新のファッションを身にまとっている。物腰は丁寧で、わたしは同性ながらドギマギしてしまう。
「は、はじめまして。え、っと、」
オカルト研究会の掲示板のアカウント名は『7ch』というものだった。読み方がわからなくてわたしは、口ごもってしまう。ななちゃんねるで合っているだろうか。それとも特殊な読み方でもあるのだろうか。第一印象から失礼なことを言うわけにはいかない。オフ会あるあるなのかもしれないが、わたしはなんと呼びかければいいかわからなかった。
「ナナでいいわ。よろしくね」
「よろしくお願いします!」
お昼過ぎに集合したわたしたちは地下鉄を利用して、まずは動物園へと向かった。ナナさんのリクエスト、というか、登山に同行する交換条件ということで、名古屋随一の動物園へと向かったのだ。
彼女がいつも『7ch』として書き込む都市伝説には、ローカルなものが多い。それなのに彼女はその動物園には初めていくのだという。まぁ、たしかに近場にありすぎる観光名所にはなんだかんだで行かないことが多いけれど。
「どこから周りましょうか」
「すごーい、こんなに賑わっているのね!」
「……いつもはこんなに賑わってはいないんですが。なにかイベントでもやってるんですかね」
綺麗で大人な印象の彼女だったが、さまざまな動物を前にテンションが上っているその姿は、まるで遠足で来たこどものようだった。アルパカやハシビロコウといった比較的マイナーな動物の前に無彩色な服装の人が集まっていて、まるでそれらの動物が擬人化されたアニメでも放送されているかのようだった。
彼女が脚を止めたのは、キリンさんの前だった。
「好きなんですか?」
呆けたようにキリンさんを見つめている彼女に声をかけた。
「……どうしてこんなに大きくなったのかしら」
「高い葉っぱを食べるためですよ?」
「そうなの?」
いまどきこどもでも知っている知識だったが、ナナさんは知らないようだった。
ひとしきり動物園を回ると、彼女はほくほく顔だった。
「楽しめましたか?」
「ええ、とっても。世の中にはいろんな動物がいるのねえ。さて、それでは向かいますか。河村さんの甘い想いを叶えにね」
「えぇ、恥ずかしいですよぉ」
わたしの手を引っ張って、ナナさんは走り出していった。
※
「河村さんの好きな人はどんな人なの?」
「すごい人です。尊敬しています。なんとなくで入った部活ですけれど、あんなに真剣に取り組んでいる人はあの人以外にはいません。部誌がある程度読まれているのも、彼の記事があるからです。取材力も、文章力も、構成力も、全部わたしなんかじゃ及びません。すごく努力をしても、きっと、ダメ。それほど、あの人の『好き』は本物なんです」
「彼は都市伝説をほんとうに信じているのね」
「でも、それ以外がからっきしなんです。すごく可愛いんですよ」
※
――あるメニューを頼んで『登頂』できれば、甘い想いが実るみたい。
彼女曰く、そのメニューのオーダーの仕方とは、ある特殊な方法らしい。考えてみればそれは当たり前で、そうでなければ、いまごろ名古屋は想いが結ばれた者たちで溢れかえっていることだろう。名古屋人で、『あの喫茶店』を訪れたことがない者なんてほとんどいないのだから。
からんころんからーん。
「いらっしゃい」
マスターに案内されて、わたしたちは席についた。休日のティータイム、店内は非常に賑わっていて、並ばずに座れたのはラッキーだった。周りを見回すと、極彩色の食べ物がそれぞれのテーブルに置かれていて、わたしはガタガタと震えだしてしまった。
「ナナさん、あれ、ちょっと多くありませんか?」
わたしが指差したテーブルには、山盛りの極彩色パスタが置かれていた。震えるわたしに彼女はさらりと微笑んだ。
「心配しないで。遠近法よ」
「なるほど。……ん、逆では?」
わたしがガクブルしているあいだに、彼女は店員さんを呼び、『この子とわたしに例のものを』とオーダーした。それを聞いた瞬間、その店員さんはすべてを察したように眼を光らせた。メニュー表に載っていない裏メニュー。それこそが甘い想いを叶えるおまじないだ。
「でも、おまじないだけじゃ足りないわ、河村さん」
「え?」
「『登頂』をしなくてはね」
『例のメニュー』とオーダーしたものが、わたしたちの前に運ばれてくる。暴力的なクリーム。視神経がパンクを起こしそうな極彩色。麺に練り込まれたアメリカのお菓子のような色。そして、量。……度し難い。『ごゆっくり』と言った店主が奥に戻っていく。
わたしの前に、壁が立ちはだかる。いや、壁というより、それはまさに山だ、みえる……、この向こうに大村部長と結ばれているわたしの姿が!
「いただきます!」
フォークで絡め取る。甘味の練り込まれたパスタが巻かれ、甘いクリームがそれに巻き込まれる。見た目だけでその甘さが想像できる。誕生日にさえケーキを辞退するわたしがこれを食べられるだろうか。フォークを握る手がふるふると震える。
「あ、あの、ナナさん」
隣を見ると、『ごちそうさま』と彼女は手を合わせていた。
「はやっ!」
「意外と美味しかったわ。エキセントリックでアバンギャルドな味で」
「マジですか……」
しかし、わたしはそのギャラクティカなパスタを口に運ぶことができずにいた。彼女は急かすでもなく諦めるでもなく見守ってくれていたが、どうしてもわたしには無理なことだった。そもそも甘いものが嫌いなわたしが、どうしてこんな甘みの極みみたいなものを食べなければならないのか。だんだん腹が立ってきた。
――何もこんなことをしなくてもいいじゃないか。
誰かがわたしにそう囁く。フォークが震える。わたしはそのことに気がついてしまった。こんなことをしなくても、大村部長に適切なアプローチをすれば想いは伝わるだろう。そのほうが効果は確実で、期待値も高い。っていうか、ここでこのパスタ食べたからって何が起こるというのだ。
でも、わたしは一度はその邪道に賭けた。正攻法がわかっていながら勇気がでないからと、こんな甘ったれた方法に頼っているのである。そしていまはその邪道のほうがハードルが高いからと、正攻法はどうだろうと甘えた考えを始めてしまっている。
自分でどうしたらいいのか、わからなくなってしまっていた。
「……ねぇ、ナナさん、都市伝説なんて嘘でしょう? 作り話なんでしょ。こんなことをしても、きっと部長との距離は縮まらない」
「そうね、嘘よ」
「はい!?」
「でも本当」
彼女はわたしに優しく微笑みかける。
「都市伝説は、勇気をもって信じれば応えてくれる。キリンさんはどうして首が伸びたの? それを求める強い想いがあったからでしょ? 信じていなければ、きっとキリンさんの首は伸びなかったわ」
「でも……」
勇気をもって。
それができないから、わたしはこんなことになっているのだ。
※
わたしは、逃げ出した。
ナナさんの声が聴こえたけれど、わたしは振り向かなかった。
※
そして、もうひとつ、わたしの名前が聴こえた。
「しかし、都市伝説なんて」
「部長のお前がそんなこといってどうすんだよ。ほら、ひとくち行ってみろって」
「こんなことをしなくても河村は――」
脚を止める。
聞き間違い? 見間違い?
わたしたちの席のすぐ後ろのボックス席には、確かに我がオカルト研究会の部長と副部長が座っており、いまの会話を聞く限り、わたしと同じく例の都市伝説を試そうとしている。
「せんぱい?」
「かわむらくん!?」
考えるよりも先にわたしは話しかけてしまっていて、驚いた部長はその衝撃で、口の前で止まっていたフォークをぱくりと咥えてしまっていた。その様子がほんとうにおかしくて、わたしは涙を拭う。眼を白黒させる部長に、信じられないといった表情の副部長。
「せんぱい、登山は無理だって言っていたのに……」
「河村君だって苦手だって言っていたじゃないか!」
安心したやらびっくりしたやら。数え切れないほどたくさんの感情がないまぜになってわたしは笑ってしまう。
「わたしだって苦手ですよ! でもここに来たんです! 都市伝説を信じているから――」
わたしはずんずんと自分の席に戻り、自分のエキセントリックでアバンギャルドなパスタの皿を取る。事情を把握したらしいナナさんと目があって、『頑張ってね』と告げられた。わたしは元気いっぱいに『はい!』と頷いて、そのパスタの皿を部長たちのボックス席にだんと置く。
「食べましょ!」
「しかしだな……」
「天下のオカ研なのに、都市伝説が信じられないんですか!」
はじめて食べた『あの喫茶店』のパスタのお味は、筆舌に尽くしがたいものだった。隣でわたし以上に四苦八苦しているひとがいなければ、きっと遭難していたことだろう。こうしてわたしの青春の1ページに、甘酸っぱい思い出が――、いや、甘すぎる思い出が刻まれたのだった。
※
席に戻ると、彼女はもういなかった。
机の上に、たいせつなものを残して。
※
春が来て。
「せんぱい、お待たせしました」
「ん、いま来たところだから大丈夫」
金時計の下で待ち合わせをしていたわたしたちだったが、ものすごい人混みで思ったように歩けなかった。みんながみんなここを集合場所としているので、混雑しているのだ。これではなかなか目当ての人に会えない人もいることだろう。わたしはすぐに先輩を見つけられたけどね。
そういえば、あのあと知ったことだったけど、大村部長は『あの喫茶店』の都市伝説以外にも、恋が実る系の都市伝説を片っ端から実践していたらしい。なんて可愛い人なんだ。それを聞いて、わたしも、ほとんど同じことをしていたことを告白した。
「映画行きましょ」
その経路上には、名古屋人なら誰もが知っている女性が佇んでいる。背の丈およそ6メートルで、その視線は遠くを見通すことができる。スリーサイズは上から207・180・215のスラッとしたボディ。FRP硬質塩ビ樹脂のような白い肌。常に最新のファッションを身にまとう、気品あふれるその姿。
「……もしかして」
気のせいかもしれないけれど、ほっぺに抹茶小倉クリームがついているように見えた。
彼女もキリンさんのように、何か強い想いを実現するために、ここに立っているのだろうか。
あの日、甘い想いが実った日、ナナさんは『あの喫茶店』から唐突に消えた。机の上に伝票を残して。結局彼女が食べた分までわたしが払ったのだが(いつのまにかおかわりまでしていたようだ)、いつかまた彼女に逢って、お礼をいいつつ、きっちりその分を請求することにしよう。
そう、こころに決めたのだった。